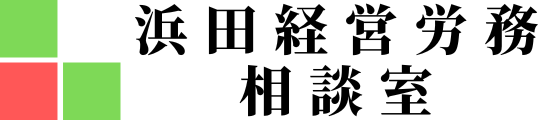目次
<2024年4月に内容を改訂しました>New
両立支援等助成金とは
両立支援等助成金とは、労働者の職業生活と子育て・介護などの家庭生活を両立させるための制度の導入や、事業所内保育施設の設置・運営、女性の活躍推進のための取り組みを行う事業主等に対して助成するものです。
24年から<育休中等業務代替支援コース>及び<柔軟な働き方選択制度支援コース>が新設されています。
※<新型コロナウイルス母性管理休暇取得制度支援コース>は、23年11月30日で申請期間は終了しました。
<育児休業等支援コース>
労働者の育児休業・職場復帰の支援プランの策定・実行する中小企業を支援するコースです。
<出生時両立支援コース>
子育てパパが育児休業を取得しやすい雇用環境整備を行う中小企業を支援するコースです。
<育休中等業務代替支援コース>
育児休業や育児短時間業務を取得・利用する方の業務代替する体制整備を行う中小企業を支援するコースです(上の<育児休業等支援コース(コロナ対応以外)>及び<出生時両立支援コース(第1種)>と併用可能です)。
<柔軟な働き方選択制度支援コース>
育児休業を行う労働者の柔軟な働き方を選択できる5つの制度のいくつかを導入する中小企業を支援するコースです。
<不妊治療両立支援コース>
不妊治療のために利用可能な休暇制度などを整備する中小企業を支援するコースです。
<介護離職防止支援コース>
労働者の円滑な介護休職の取得・復帰などに取り組んだ中小企業を支援するコースです。
<育児休業等支援コース>
①助成金の趣旨
・労働者の育児休業の円滑な取得・職場復帰のための取り組みを行った中小企業に対して助成するものです。具体的には、以下の場合に助成されます。
イ.育休取得時、ロ.職場復帰時:
「育休復帰支援プラン」を策定し、プランに沿って対象労働者の円滑な育児休業の取得及び、復帰に取り組んだ場合
ハ.業務代替支援:
<育休中等業務代替支援コース>が開始されたため、23年12月末で終了となりました。
ニ.職場復帰後支援:
育児休業からの復帰後の支援として、法の基準(小学校就学前の子ども一人当たり年間5日、二人以上の場合は年間10日)を上回る子の看護休暇制度や保育サービス費用助成制度を導入し、労働者に利用させた場合
②対象企業
・該当雇用保険被保険者を雇用する中小企業
よくあるご質問2-1:厚労省の助成金における中小企業とは
中小企業の範囲は、イ.または、ロ.を満たすことが求められます。
| イ.資本金の額・出資の総額 | ロ.常時雇用する労働者数 | |
| 小売業(飲食店を含む) | 5000万円以下 | 50人以下 |
| サービス業 | 5000万円以下 | 100人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
但し、人材確保等支援助成金(中小企業団体助成コース)における中小企業の範囲は、経済産業省の補助金における中小企業の範囲と同一となります。
よくあるご質問1-8:経済産業省の補助金における中小企業の範囲とは
以下のどちらかを満たすことが対象です。
| 資本金額 | 従業員数 | |
| 製造業・ソフトウェア業 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| サービス業 | 5000万円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5000万円以下 | 50人以下 |
| ゴム製品製造業 | 3億円以下 | 900人以下 |
| 旅館業 | 5000万円以下 | 200人以下 |
③助成額
| ⅰ | 育休取得時 | 30万円 | |
| 職場復帰時 | 30万円 | ||
| ⅱ | 業務代替支援 | (新規雇用(派遣を含む)) 50万円/人 | (手当支給等) 10万円 |
| 有期労働者加算:10万円 | |||
| ⅲ | 子の看護休暇制度 | 制度導入時 30万円 | 取得した休暇時間数に1000円を乗じた額 |
| ⅳ | 保育サービス費用助成制度 | 制度導入時 30万円 | 事業主が負担した費用の2/3 |
| 育児休業等に関する情報公表加算 | ⅰからⅳのいづれかの加算として2万円(1回限り) | ||
| ⅴ | 新型コロナ感染症対応特例 | 一人当たり10万円 | |
ⅲ,ⅳは、制度導入は1事業主当たり1回限り、制度利用時は初回から3年以内に5人まで支給
ⅴは、10人(上限100万円)まで
※生産性要件を満たした場合の割り増しは、23年3月31日で終了となりました。
④要件
・3か月以上の育休と、復帰後6か月の雇用が前提条件となります。
⑤手続き
イ.事前準備
・育児休業規則の策定・労基署への届け出
・育児復帰プランを策定し、労働者に周知するとともに、対象者に引継ぎを実施
ロ.育児休業(連続3か月以上)取得時
・育児復帰プランに基づき、職務や業務に関する情報・資料の提供
・休業終了前の面談実施
・育休開始日から3か月経過の翌日から2か月以内に助成金申請
ハ.復帰時
・原則として原職に復帰
・その後、雇用保険被保険者として6か月以上継続雇用
・育休終了日の翌日から6か月経過後2か月以内に助成金申請
となります。
<出生時両立支援コース>
①助成金の趣旨
・男性労働者の育児休業取得率が低い現状から、男性労働者の子の出生後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を取得させた中小企業に対して助成するものです。
・さらに3年以内にその取得率の30%アップに取り組んだ中小企業に対して追加助成されます。
※第Ⅰ種受給年度に育休対象の男性が5人未満かつ取得率70%以上の事業主は、3年以内に2年連続70%以上となった場合も対象
②対象企業
・該当雇用保険被保険者を雇用する中小企業(大企業への助成は2021年度で終了しました。)
よくあるご質問2-1:厚労省の助成金における中小企業とは
中小企業の範囲は、イ.または、ロ.を満たすことが求められます。
| イ.資本金の額・出資の総額 | ロ.常時雇用する労働者数 | |
| 小売業(飲食店を含む) | 5000万円以下 | 50人以下 |
| サービス業 | 5000万円以下 | 100人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
但し、人材確保等支援助成金(中小企業団体助成コース)における中小企業の範囲は、経済産業省の補助金における中小企業の範囲と同一となります。
③助成額
| 第1種 | 育児休業取得 | 20万円 | |
| 育児休業等に関する情報公表加算 | 2万円 | ||
| 第2種 | 育児休業取得率の30%以上上昇等を達成するまでの期間 | 1事業年度以内 | 60万円 |
| 2事業年度以内 | 40万円 | ||
| 3事業年度以内 | 20万円 | ||
・第1種受給時にプラチナくるみん認定事業主であった場合は、第2種助成額が15万円加算されます。
※「代替要員加算」は、<育休中等業務代替支援コース>が開始されたため、23年12月末で終了となりました。
※生産性要件を満たした場合の割り増しは、23年3月末で終了となりました。
④要件
イ.第1種
(イ) 一人目
・雇用する男性被保険者について、労働協約又は就業規則の定めるところにより、子の出生から8週間の翌日までに開始する連続した5日以上(休日が入っていても可。ex.金土日月火)の育児休業を取得させていること。
・雇用環境整備措置を2つ以上実施していること(措置を4つ以上実施した場合は助成額を30万円に増額)。
(ロ) 二人目
・連続10日以上の育児休業
・雇用環境整備措置を3つ以上実施
(ハ) 三人目
・連続14日以上の育児休業
・雇用環境整備措置を4つ以上実施
ロ.第2種
・第1種助成金を受けている事業者が、その申請をした翌年度以降3事業年度以内において、男性被保険者の育休取得率が30%以上増加し、1日以上の育休を取得した男性保険者が2人以上いること。
⑤手続き
イ.事前準備
・育児休業規則の策定・労基署の届け出
(女性労働者が対象の育児休業等支援コースとは異なり、育児復帰プランの作成等は不要です。)
ロ.育児休業(連続5日以上)取得時
・育休開始日から5日経過の翌日から2か月以内(育休中でも可)に助成金申請
<育休中等業務代替支援コース>
①助成金の趣旨
・育児休業や育児短時間勤務を取得・利用する方の業務の代替する体制整備として、周囲の労働者に手当を支払って代替させた場合、代替する労働者を新規雇用(または新規の派遣受け入れ)した中小企業に対して助成するものです。
・具体的には、
(1)手当支給等(育児休業):育児休業を取得する労働者の代替
(2)手当支給等(短時間勤務):育児短時間勤務を利用する労働者の代替
(3)新規雇用(育児休業):育児休業を取得する労働者の代替
の3つのメニューがあります。
②対象企業
・該当雇用保険被保険者を雇用する中小企業
よくあるご質問2-1:厚労省の助成金における中小企業とは
中小企業の範囲は、イ.または、ロ.を満たすことが求められます。
| イ.資本金の額・出資の総額 | ロ.常時雇用する労働者数 | |
| 小売業(飲食店を含む) | 5000万円以下 | 50人以下 |
| サービス業 | 5000万円以下 | 100人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
但し、人材確保等支援助成金(中小企業団体助成コース)における中小企業の範囲は、経済産業省の補助金における中小企業の範囲と同一となります。
③助成額
| (1)手当支給等(育児休業) | ・業務体制整備経費:5万円 ・業務代替手当:支給額の 3/4 (注1) (月10万円上限、12カ月まで) |
| (2)手当支給等(短時間勤務) | ・業務体制整備経費:2万円 ・業務代替手当:支給額の 3/4 (注1) (月3万円上限、子が3歳になるまで) |
| (3)新規雇用(育児休業) | ・育児休業期間中に業務代替した期間に応じて 9万円~67.5万円(注2) |
| (1)~(3)に共通(注3) | ・有期雇用労働者加算:10万円 ・育児休業等に関する情報公開加算:2万円 |
(注2)プラチナくるみん認定事業主は、11万円~82.5万円
(注3)全て合わせて、1事業主1年度につき休業取得者と制度利用者合計10人まで、初回対象者が出てから5年間。(1)~(3)いずれも1回限り。さらに、同一の子にかかる育児休業については、(1)と(3)は一方のみが対象。
④要件
(1)手当支給等(育児休業):育児休業を取得する労働者の代替
イ.育児休業取得者や業務代替者の業務の見直し・効率化を行う。
ロ.代替業務に対応した手当の制度を就業規則等に規定する。
ハ.育児休業取得者に7日(うち所定労働日が3日)以上育児休業を取得させる。
二.ㇵの育児休業中の業務代替機関について、手当等による賃金増額を行っている。(手当ては代替内容を評価するものであり、総額で1万円以上支給していること(1カ月未満の場合は1日当たり500円)
ホ.ㇵの育児休業期間が1カ月以上の場合、育児休業終了後、原則として原職等に復帰させ、3カ月以上継続雇用する(就業規則もその旨規定化する)。
(2)手当支給等(短時間勤務):育児短時間勤務を利用する労働者の代替
イ.育児休業取得者や業務代替者の業務の見直し・効率化を行う。
ロ.代替業務に対応した手当の制度を就業規則等に規定する。
ハ.制度利用者に1カ月以上の育児のための短時間勤務制度を利用させる(1日(所定労働時間7時間以上の労働者が、1日1時間以上短縮した場合が対象)。
二.ㇵの育児休業中の業務代替機関について、手当等による賃金増額を行っている。(手当ては代替内容を評価するものであり、総額で3千円以上支給していること(1カ月未満の場合は1日当たり150円)
(3)新規雇用(育児休業):育児休業を取得する労働者の代替
イ.育児休業取得者の業務代替をする労働者を新規で雇入れる(新規派遣を含む)。
ロ.育児休業取得者に7日(うち所定労働日が3日)以上育児休業を取得させる。
ハ.イ.で雇入れた労働者(下記に該当)が、ロの期間中に業務を代替する。
(育児休業取得者と同一部署で勤務している。所定労働時間が育児休業取得者の2分の1以上である)
ホ.ロの育児休業期間が1カ月以上の場合、育児休業終了後、原則として原職等に復帰させ、3カ月以上継続雇用する(就業規則もその旨規定化する)。
<柔軟な働き方選択制度支援コース>
①助成金の趣旨
・育児期の柔軟な働き方に関する制度を導入した上で、「育児に関する柔軟な働き方支援プラン」により制度利用者を支援し、開始6か月間で一定以上の利用実績があった中小事業主に助成するものです。
②対象企業
・該当雇用保険被保険者を雇用する中小企業
よくあるご質問2-1:厚労省の助成金における中小企業とは
中小企業の範囲は、イ.または、ロ.を満たすことが求められます。
| イ.資本金の額・出資の総額 | ロ.常時雇用する労働者数 | |
| 小売業(飲食店を含む) | 5000万円以下 | 50人以下 |
| サービス業 | 5000万円以下 | 100人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
但し、人材確保等支援助成金(中小企業団体助成コース)における中小企業の範囲は、経済産業省の補助金における中小企業の範囲と同一となります。
③助成額
・柔軟な働き方選択制度を2つ以上導入し、対象労働者が利用:20万円
・柔軟な働き方選択制度を3つ以上導入し、対象労働者が利用:25万円
※1年度当たり1事業主5人まで対象
※育児休業等に関する情報公開加算(1回限りで2万円)の適用があります。
④要件
イ.育児を行う労働者の柔軟な働き方選択できる制度(下記AからEから2つ以上)を導入する
ロ.「育児に関する柔軟な働き方支援プラン」により、制度利用及び方針を社内周知する
ハ.助成金対象労働者(制度利用者)と面談を実施し、「面談シート」を記録する
二.面談結果を踏まえ、制度利用者の「育児に係る働き方支援プラン」を作成する
ホ.開始から6か月間で柔軟な働き方を可能とする制度、下記の基準以上利用
| 制度名称 | 導入すべき内容 | 利用実績の基準 | |
| (A) 始業・終業時刻の変更等 | フレックスタイム制 | 日々の始業・終業時刻や労働時間を労働者が決定 | 合計20日以上 |
| 時差出勤制度 | 始業・終業時刻の1時間以上の繰り上げ又は繰り下げ | 合計20日以上 | |
| (B) 育児のためのテレワーク等 | 自宅等での勤務を可能とする | 合計20日以上 | |
| (C) 短時間勤務制度 | 所定労働時間を1日1時間以上短縮 | 合計20日以上 | |
| (D) 保育サービスの手配・費用補助制度 | 一時的な保育サービスを手配し、費用の全部または一部を補助 | 負担額の5割以上かつ、 3万円以上または10万円以上の補助 | |
| (E) 子の養育のための有給休暇 | 子の養育を容易にする休暇制度 | 有給、年10日以上取得可能、時間単位取得可能な制度 | 合計20時間以上 |
| 法を上回る子の看護休暇制度 | 有給、年10日以上取得可能、時間単位取得可能な制度 | 合計20時間以上 | |
<不妊治療両立支援コース>
①助成金の趣旨
・不妊治療のために利用可能な休暇制度・両立支援制度(※)の環境整備に取り組み、不妊治療を行う労働者の相談に対応し、それらの制度を労働者に取得又は利用させた中小事業主に対して助成するものです。
※不妊治療のための休暇制度(特定目的・多目的とも可)、所定外労働制限、時差出勤、短時間勤務、フレックスタイム制、テレワークのいずれかを指します。
②対象企業
・該当雇用保険被保険者を雇用する中小企業
よくあるご質問2-1:厚労省の助成金における中小企業とは
中小企業の範囲は、イ.または、ロ.を満たすことが求められます。
| イ.資本金の額・出資の総額 | ロ.常時雇用する労働者数 | |
| 小売業(飲食店を含む) | 5000万円以下 | 50人以下 |
| サービス業 | 5000万円以下 | 100人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
但し、人材確保等支援助成金(中小企業団体助成コース)における中小企業の範囲は、経済産業省の補助金における中小企業の範囲と同一となります。
③助成額
| イ.環境整備、休暇の取得等 | ロ.長期休暇の加算* |
| 30万円 | 1人当たり30万円 |
※生産性要件を満たした場合の割り増しは、23年3月31日で終了となりました。
④要件
環境整備、休暇の取得等
・不妊治療と仕事の両立の支援についての方針を示し、労働者に周知させるための措置を講じていること
・不妊治療と仕事の両立についての労働者の相談に対応し、両立を支援する「両立支援担当者」を選任するとともに、社内ニーズの把握、利用可能な制度の周知を行うこと
・両立支援担当者が不妊治療を受ける労働者の相談に応じ、「不妊治療支援プラン」を策定し、プランに基づき休暇制度・両立支援制度を合計5日(回)以上、労働者に取得又は利用させたこと
<介護離職防止支援コース>
①助成金の趣旨
「介護支援プラン」を策定し、プランに基づき労働者の円滑な介護休業の取得・復帰に取り組んだ中小企業事業主、又は介護のための柔軟な就労形態の制度を導入し、利用者が生じた中小企業事業主に助成するものです。
②対象企業
・該当雇用保険被保険者を雇用する中小企業
よくあるご質問2-1:厚労省の助成金における中小企業とは
中小企業の範囲は、イ.または、ロ.を満たすことが求められます。
| イ.資本金の額・出資の総額 | ロ.常時雇用する労働者数 | |
| 小売業(飲食店を含む) | 5000万円以下 | 50人以下 |
| サービス業 | 5000万円以下 | 100人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
但し、人材確保等支援助成金(中小企業団体助成コース)における中小企業の範囲は、経済産業省の補助金における中小企業の範囲と同一となります。
③助成額
| イ.介護休業 | 休業取得時 | 30万円 | *1年度各5人まで |
| 職場復帰時 | 30万円 | ||
| ⅰ)イ.への加算 業務代替加算 | 新規雇用20万円、手当支給等5万円 | ||
| ロ.介護両立支援制度 | 30万円 | *1年度5人まで | |
| ⅱ)イ及びロへの加算 個別周知・環境整備加算 | 15万円 | ||
| ハ.新型コロナウイルス感染症対応特例 | (労働者1人当たり)*1年度5人まで 5日以上10日未満 20万円 10日以上 35万円 | ||
④要件
イ. 介護休業:対象労働者が介護休業を合計5日以上取得し、復帰した場合
ⅰ)イ.への加算(業務代替加算):介護休業取得者の代替要員の新規雇用(派遣を含む)又は代替する労働者への手当支給等を行い、かつ、休業取得者を原職等に復帰させた場合
ロ. 介護両立支援制度:介護のための在宅勤務、法を上回る介護休暇、介護フレックスタイム制、介護サービス費用補助など、介護のための柔軟な就労形態の制度を導入し、合計20日以上利用した場合
ⅱ)イ.及びロ.への加算(個別周知・環境整備加算):介護を申し出た労働者に対する個別周知及び介護と仕事を両立しやすい雇用環境整備を行った場合
ハ. 新型コロナウイルス感染症対応特例:新型コロナウイルスの感染症への対応として、家族を介護するために特別休暇を取得した場合
ブログNo.15:両立支援等助成金の活用のポイント
ブログNo.16:両立支援等助成金の改正点など最新情報
ブログNo.22:育児介護休業法2022年度法改正の主なポイント(2022年5月1日)
ブログNo.24:22年7月から男女の賃金格差と副業・兼業の許容状況の情報公表が求められます(2022年8月1日)